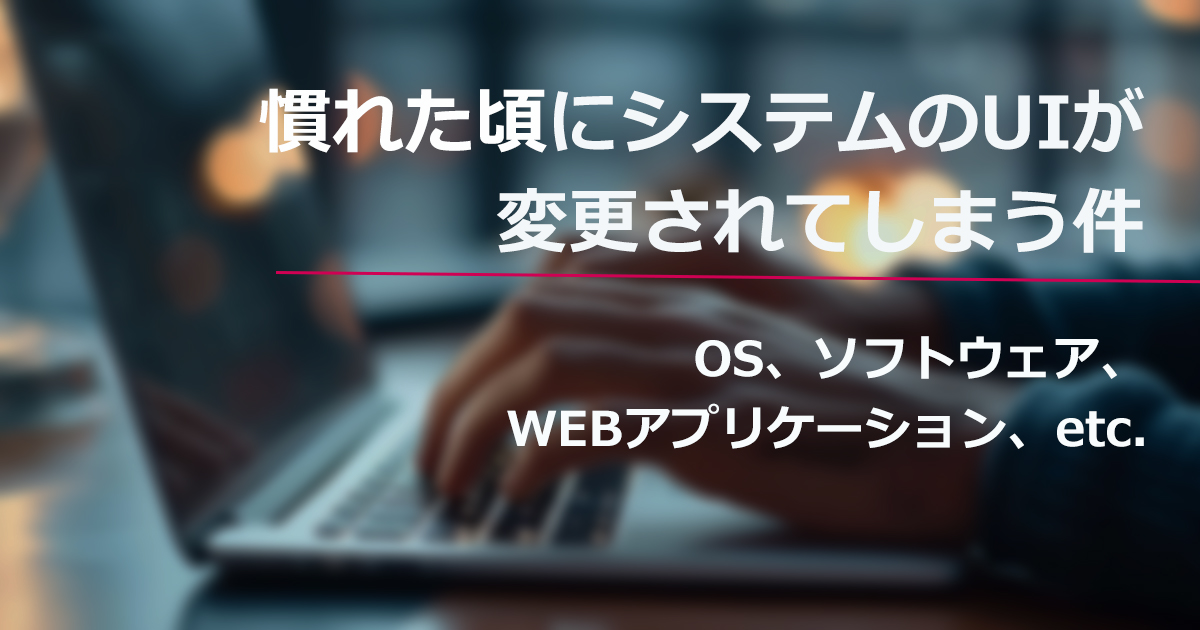本の流通について調べてみた
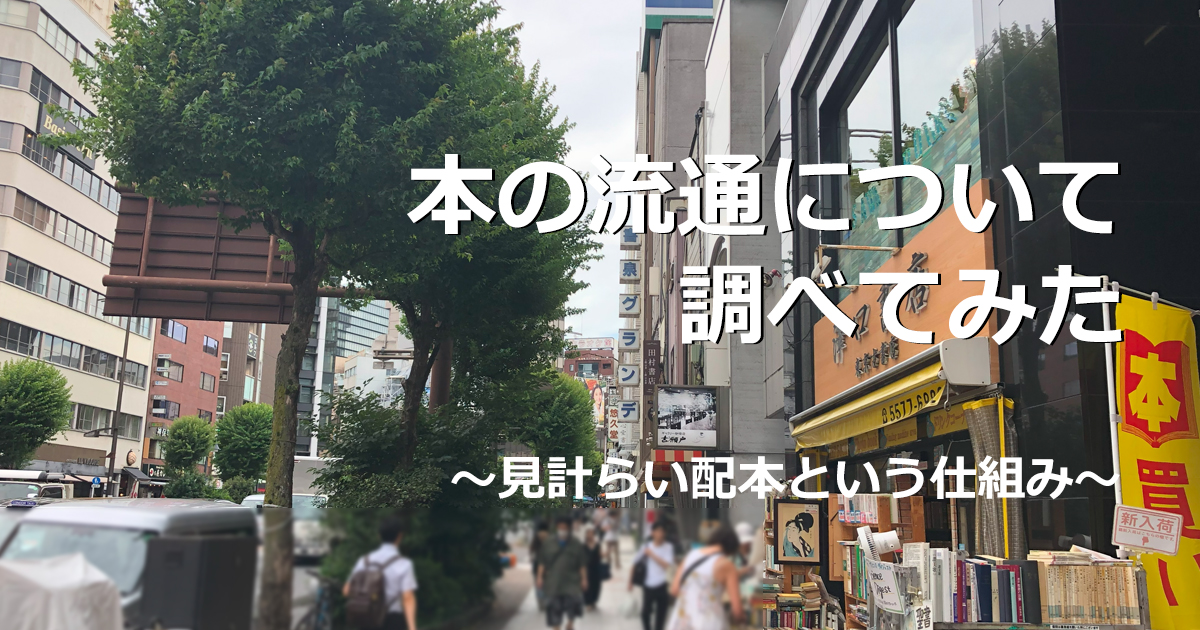
~見計らい配本という仕組み~
こんにちは、KJです。
弊社はこれまで自社が得意とする印刷技術をいかして、nu boardや消せる紙といった文具の開発・販売のほか、点字・触知図印刷などを手がけてきましたが、この春、従来とは違った形での事業を開始しました。
2か月前の5月に「おやさいぬりえダンス」という本を発売したのですが、クレヨンで描いた塗り絵をスマートフォンで読み込むと、塗り絵がブラウザ上で踊るという仕組みになっています。
開発は当社が運営する「ブログ製本サービス」のシステムを開発しているチームが手掛け、先日にはオリジナルサイトもオープンしました。
ぬりえダンス.com
https://nuriedance.com/

このような商品を販売する場合、従来は文具店を中心とした販売チャネルを利用していたわけですが、今回発売した「おやさいぬりえダンス」はISBNコードを取得し、書店経由での販売としました。
別の言い方をすれば当社が出版社としての立ち位置となったわけで、これまでおこなってきた仕事の流れとはずいぶん違いがあります。
ところで筆者の趣味は読書なのですが、会社のある水道橋から地下鉄で一駅ということもあって本の街・神保町にはよく出かけます。
お気に入りの書店も何店かあるのですが、”出版された本がどういう流れで販売されているのか?””書店の現状はどうなっているのか?”といった事柄に興味もあって、ちょっと調べてみることにしました。
すると、今まで思いもよらなかった事情が見えてきました。
本の流通は、出版社→取次→書店という流れになるのですが、まず最初に驚いたのが「見計らい配本(みはからいはいほん)」とよばれているものです。これは取次が選んだ新刊書籍を書店に対して配本する仕組みのことで、おおよそ毎日200冊程度が送られくるそうです。
ここでポイントとなるのは、配本される本は書店からの注文ではなく、あくまでも取次が選んだ本であるということです。書店からすれば注文していない本が一方的に送られてくるわけですから、自店舗の客層に合わない本も送られてきたりするわけです。
もちろん、広く知られているように書店側は不要な本は返品できますが、配本された分の費用は支払う必要があるとのこと。なお、返品期間は配本されてから105日以内(約4か月)というのが標準的な期限のようです。
また、出版社側からみた場合、取次に入れる初版の最低数量は3,000部程度は必要とのことで、これだけあっても日本の書店数(2023年で10,918※1)には遠くおよびません。
さらに、取次から出版社への支払い期日ですが、大手出版社は別として中小クラスだと標準で返品が確定してから3か月後(本を卸してから7か月後)となり、こちらもなかなか大変なようです。
※1:出版科学研究所 https://shuppankagaku.com/knowledge/bookstores/
なお、専門書を扱う出版社が主体のようですが、2020年代に入ってからは(取次経由で)配本する書店を決めて新刊を送る「指定配本」の比率も高まってきているようです。
●書店の現状
さて、書店を取り巻く現状ですが、”書店のない街が増えてきている”というニュースを目にしたこともあり調べてみたところ現状はかなり厳しいようで、書籍の売上だけではほぼ赤字となってしまう店舗が多いようです。
というのも、書店が得る利益は販売価格のおよそ20%程度ということなのですが、店舗の運営費(テナント料・光熱費・人件費など)が高騰していることもあって、本の売上から得る利益だけでは到底経費をまかなえないといった実態もあるようです。
そのため書籍以外に文具を扱ったり、大手の書店では外商部門が企業や大学、自治体などを対象として営業活動を行ったりするほか、図書館を専門とする会社を設立するなど、通常の書籍の販売だけに頼らない方法を模索しているようです。
弊社は印刷会社ですが、仕事の主流は商業印刷物とよばれる分野が中心で、書店に並ぶ書籍関係の印刷・製本に関してはあまり経験がありません。そういった意味で今回、出版社・取次・書店間における流通の仕組みを知ることは、とても勉強になりました。
ただし、本の流通にかかわる部分は部外者にはよくわからない部分もあり、今回の記事に掲載しなかった事項も数多くあります。
このあたりについてはまた機会があればブログで取り上げたいと思います。
では、KJでした。